ああ、もう一週間前のことだ。「ブエノスアイレスのマリア」。現代タンゴを切り開いた作曲家で希代のバンドネオン奏者アストル・ピアソラが、タンゴの現代詩人オラシオ・フェレールと共に1968年に創り上げた彼の最高傑作と言われるタンゴ組曲。
 先週日曜日、満員の埼玉・川口リリア音楽ホールで、バンドネオン奏者・小松亮太率いる11名編成のタンゴオルケスタ(オーケストラ)と、男女二人の歌手、そしてナレーター合わせて総勢14名のスペシャルユニットによる公演終了。その中に身を置くことができて、ありがたかった。
先週日曜日、満員の埼玉・川口リリア音楽ホールで、バンドネオン奏者・小松亮太率いる11名編成のタンゴオルケスタ(オーケストラ)と、男女二人の歌手、そしてナレーター合わせて総勢14名のスペシャルユニットによる公演終了。その中に身を置くことができて、ありがたかった。
タンゴの化身でもあるマリアの生と死と復活の不思議な物語。歌やナレーションなどの随所に現れる世界創造やクリスマス、受難、復活などに関わる聖書的・キリスト教的な隠喩、メタファーの数々がこの作品に深遠な宗教性を帯びさせている。
しかし、この小松亮太バージョンが特別なのは、それがさらに「震災」というとてつもない出来事、そしてその記憶と、結びついているからでもある。元々2011年3月19日に最初の公演は予定されていたのが震災で中止。その決定直後に行われた、公演予定も聴衆の存在もないリハーサルでは、音楽に包まれて怖さも不安も忘れるひと時を過ごしたのだった。
震災にまつわる痛みや悲しみの記憶。それはもはやこの作品に否応なく内在化され、一体化してしまっている。あれから12年のマリア。それから12年間を生きてきた者たちによるマリア。その後2013年と翌年に「ブエノスアイレスのマリア」公演が数回繰り返されて以来久しぶりの再会。なんともいえずほっとするのは、それが単にこのとてつもない作品に一緒に挑戦してきた仲間たちであるからだけではないと思う。それはきっと、それがこのメンバーにとって震災と、そこで生まれた様々な悲しみをその胎内に宿したマリア、「震災のマリア」だからだ。本番中、やっぱり何度も涙が溢れそうになったのは、マリアを通じて改めて「震災」「3・11」とそのキズに触れていたからかもしれない。
マリアは終盤、「アレグロ・タンガービレ」で一気に走りだし、そして「受胎告知のミロンガ」で空へと舞い上がる。歌が最高潮を迎える直前の間奏の数小節は、まるで大空をみんなで飛んでいるような感覚だった。幸せだった。マリアと共に。マリアの中で。
そして最終曲「タングス・デイ」(神のタンゴ)。断片的に、この作品の記憶が再現され、やがて最後にタンゴのリズムが奏でられる中、マリアが歩み去っていく後ろ姿を見送るような気持ちになった。繰り返し打ち鳴らされる鐘は祈り、そして最後のゴングは永遠だった。
12年経った今なお、震災の映像、写真に近付くのが怖い。それは単に画像の恐ろしさだけではなく、それによって震災に連なった様々なキズの痛みが甦るからだ。しかし、「ブエノスアイレスのマリア」はそんな自分が今、震災の記憶に触れなおすことのできる道でもあったのだった。音楽に包まれ、タンゴに導かれ、仲間たちと一緒に、文字通り、守られて。
「ヌエストラ・マリア」。わたしたちみんなの、マリア。そこには、震災でいのちを断ち切られた者たち、そしてその後をキズと共に生き延びてきた者たちにつながる祈りがたしかに響いているのだった。そしてそれは昨日の3月11日も、公演から一週間経った今日3月12日も。そしてきっとこれからも、この胸に。
ありがとう、マリア。震災の、マリア。
(記)会計担当 U.N(2023年3月12日の週報より転載)
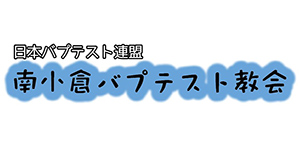
最近のコメント