相模原・津久井やまゆり園障がい者殺傷事件に関連して考えていることがもうひとつある。それは、いのちの在り処(ありか)について。
 いのちは、どこにあるのか。それを真剣に考えることが、原題のこの世界を生きる上で極めて重要になってきていることを、事件は私たちに突き付けていると思われるのだ。
いのちは、どこにあるのか。それを真剣に考えることが、原題のこの世界を生きる上で極めて重要になってきていることを、事件は私たちに突き付けていると思われるのだ。
事件の犯人、植松聖氏は犯行に際し、挨拶すること、自分の使命を名乗ることができない入所者たちを特定しては殺傷していった。植松氏はこうした人々を「心失者」と呼び、不幸しか作らず、社会の負担を増すだけの存在、生きる意味のないいのちであり、死なせた方が社会のためだと考えていた。
しかし、心は、挨拶や自ら名乗ることのできない者にはないのか。また他人の世話にならなければ全く自力で生きることのできない者には、命の意味はないのか。
心、いのち、尊厳について考えるとき、私たちはそれを人間がみずからの内に所有することができるものとして捉えがちだ。しかし、ほんとうにそうなのか。
いのちは、尊厳は、心は、個人の内に、個人のモノとして、あるのか。その人だけのものか。むしろそれは、いつも誰かとの間に見出されるmのなのではないか。
いのちの大切さも、尊厳も、心も、またその人自身さえも、孤立した自分自身の内面だけに見出すことができないおものなのではないか。他者と共にある時にこそ、見えてくるものなのではないか。
 ミヒャエル・エンデは本当の自分自身を自分の中に探そうとすると自己と言う迷宮に迷い込むことになる、本当の自己は自身の外にある、と語っている。(出典:エンデと語る)
ミヒャエル・エンデは本当の自分自身を自分の中に探そうとすると自己と言う迷宮に迷い込むことになる、本当の自己は自身の外にある、と語っている。(出典:エンデと語る)
障がい者である牧口一二は、心は人と人の間にふんわりと生まれる色とりどりの風船のようなもの、と語っている。(出典:雨あがりのギンヤンマたち)
そうであるなら、いのちは誰のモノでもなく、共に生きる存在の間に息づき、現実化し、見出されうるものだ。いのちは、人が自分勝手に握り、手中に収めることのできないもの。それは永遠に「私」のものにならず、絶対に所有することのできないもの。いのちの尊厳とは、そういうことなのではないか。
1999年、当時東京都知事であった石原慎太郎氏は、障がい者施設を視察した直後、「ああいう人たちには人格というものがあるのかね」と発言した。彼もまた、障がい者と自分自身の間に現れる人格的な関係に思いを向けることができなかったのだ。自らが殺傷した障がい者たちと自分自身の間に必ず見出すことができたはずの心やその交流を、植松氏自身が見失っていたように。
 いのちの在り処が見失われる時代は、人間存在自身が最も深く苦しむ時代だ。いのちそのものが、呻吟している。際限のない弱肉強食が世界を覆い、人間のいのちの尊厳が徹底的に傷つけられている時代の只中で、いのちを本来の在り処に見出しなおしたいと思う。
いのちの在り処が見失われる時代は、人間存在自身が最も深く苦しむ時代だ。いのちそのものが、呻吟している。際限のない弱肉強食が世界を覆い、人間のいのちの尊厳が徹底的に傷つけられている時代の只中で、いのちを本来の在り処に見出しなおしたいと思う。
いのちを人間の手から解放し、自由にするために。
私たちが癒されるために。
きっと、それがいのちを神の手に委ねる、ということなのだ。
(記)会計担当 U.N(2022年8月7日の週報より転載)
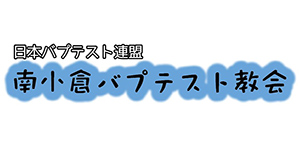
最近のコメント