水曜日の聖書の学びと祈りの会で今年の5月18日から読み始めたへブル人への手紙の学びが終わりました。田川建三訳著の「訳と註」を手引きに学んできましたが、そのまとめを巻末の「解説、後書き」も参考に簡単にまとめます。

- 著者はギリシャ語を母語として育った教養人。非ユダヤ人。引用されているのは主に詩編。しかし実は律法のことやユダヤ教の祭儀などについては余り詳しくない。
- 「へブル人への手紙」と呼ばれているが、宛先はヘブライ人(ユダヤ人)ではなく、中身も手紙ではない。むしろキリスト教の教義の論文のような文書。最後だけ手紙のスタイルになるあ、そこはおそらく著者とは別の書き手がパウロに似せて手紙のスタイルを取ることで権威化を図ったもの。
- 著者はキリスト教の教義を突き詰めて考え、その真実性をとらえようとした人物。誠実でまじめな態度が見られる。
- 著者は古代文献であるユダヤ教正典(旧約聖書)によって、キリスト(教)の真実性が裏付けられると考えた。すでに長きにわたって歴史の批判に耐えて残っている古い文書には正当性があり、これによってイエスがキリストであることが裏付けられるという考え方に基づく。しかし、ユダヤ教に関する知識は豊富ではない。
- 著者は同時に、しかし、キリスト教はユダヤ教よりはるかに優れたものであって、ユダヤ教はもはや無効である、ということも語ろうとした。ユダヤ教(旧約聖書)に立脚しながら、これを相対化し、キリスト教の正しさを論証しようとする。
- 相反するふたつの課題の狭間で著者は矛盾に陥り、それをなんとか乗り越えようとして無理をしている。「屁理屈」「つまらない」と田川氏。
- 1~2章は旧約聖書の預言がイエス・キリストによって成就した、と語るが、その後はイエス・キリストによってユダヤ教は乗り越えられた、と主張。イエスはただ一度、その死によって自ら決定的な罪の贖いとなった真の大祭司だ、と論じることがその中心。もう二度と罪の赦しの為の儀式やささげものは必要がない、と論じる。律法(正典、文書)だけでなく祭儀宗教としてのユダヤ教そのものを問題視し、イエス・キリストによってそれが克服された、と主張する。ユニークで優れた姿勢。
- 著者はこれを端的に指摘して、あっさり済ますことができず、長々と論証を試みた。ここに無理があったとはいえ、古代の宗教の大半が犠牲祭儀宗教であったことを考え合わせると、それを乗り越え無効だと宣言した点で革命的。
へブル人への手紙が乗り越えようとした犠牲の宗教を、キリスト教は乗り越えることができているだろうか。へブル人への手紙自体は、それに成功しているか。わたしたちは、この社会はどうだろうか。
イエス・キリストを信じることは、安心して生きることです。赦しを信じ、終わることのない伴いを心に留め、生きていいと心に刻んで生きることです。何かを代償に差し出し続けなければ生きる資格がないと思い込んだまま生きていないか。へブル人への手紙はそう今日のわたしたちにも語り掛けています。
(記)会計担当 U.N(2022年11月20日の週報より転載)
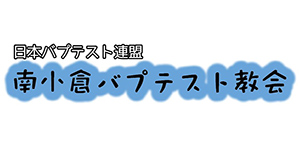
最近のコメント